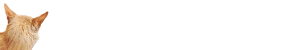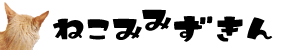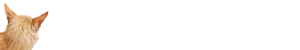2020年2月11日(火)、快晴の天気の下、小3の次女を連れて栃木市にある大平山(341m)と晃石山(419m)をプチ縦走してきました。眺めが良い山で、元旦の朝はご来光を拝みに多くの参拝客が中腹の謙信平や太平山神社にやってくるそうです。桜の季節やあじさいが咲く頃に来るのも良いでしょう。今日の様に冬晴れで空気中の水蒸気量が少ない日は遠くまで見渡すことができます。
今回の山行ルート
記録開始は山門の前辺りから。さらにバッテリーの充電不足でGPSの記録が復路の途中で切れています。
あじさい坂駐車場~太平山神社
まずはトイレの写真から(笑)。今回は國學院栃木高校前を通り過ぎた所にある、あじさい坂駐車場からスタートです。
あじさい坂駐車場の様子。ここに止めると結構長い階段や坂が待ち受けているので、車で中腹まで登って「謙信平」の駐車場に止めるとラク出来ます。
駐車場に設置されているハイキングMAPで今日たどるルートを再確認しようと思ったけど、我々は晃石山まで行く予定なのであまり参考にならず。
では出発~。信仰の山として歴史のある大平山はあちこちに社がある。この鳥居をくぐってすぐ左手にあるのは「六角堂」というお寺。
屋根が六角形をしていて珍しいお堂。明治元年の神仏分離令後に太平山神社から分離、ここに移転したそうです。横を通りすぎてあじさい坂へ進む。
延々と続く階段の坂道の両脇には枯れたあじさい。2月上旬なのでこんな感じです。
今度は右手に窟神社が現れた。ちょっと寄り道。
水の溜まった小さな洞窟があり、この中には弁財天が祀られている。
よく分からない銅像が立っていたり。
手水舎の先にある鳥居が本来の入口っぽいけど、草木が生い茂り荒れている。今は横の階段が通常の通り道になっている。
上の鳥居を反対側から見るとこんな状態。昔はここにもうちょいマシな橋があったのでは?
坂の下を振り返るとこんな感じ。谷間にあって冬の朝は肌寒い。
階段をのぼると赤い山門が現れる。
山門をくぐって階段はまだ続く。
山門(随神門)の説明板。仁王像が設置されている。
階段を登りきると大平山神社に到着。面白いことに沢山の神社がここに集結していて、登山家にお勧めするのが足腰の神社「足尾神社」。
御神石なでなで。
神社は年に1回来るか来ないかなので、お参りの作法を掲示しておいてくれると助かる。
いたる所に賽銭箱が(苦笑)
足腰の神社、足尾神社
こっちが肝心の足尾神社。
下駄が供えられているのが面白い。
足尾神社の賽銭箱の前には右足の型があり、六十二・八と彫られている。この数字の意味がどうしても分からない。今度来たら社務所の人に聞いてみよう。
登山口~太平山山頂
神社群を一通り見て回ったので登山口へ。本殿に向かって右の方に登山口の看板があり、そこの階段が登山口です。
5分くらい歩くと「奥宮入口」と表示された分岐がある。ちょいと寄り道。
石造りの奥宮。ここにも賽銭箱か~。道を進むと先ほどの登山道に合流する。
太平山神社奥宮について。
分岐に到着。このまままっすぐ登ると太平山山頂。晃石山への分岐は等高線に沿った巻道で、山頂を通る道と再び合流する。行きは山頂経由で、帰りはこの巻道を使います。
山頂への登山道にはしめ縄が張られているのでくぐって進む。
太平山の山頂周辺は樹林帯で特に眺望は無い。
大平山山頂(341m)の富士浅間神社。あっという間に着いてしまったので、休憩せずに先へ進む。浅間神社は山登りをしているとあちこちで目にしますな。例えば、、、谷川岳とか。
太平山山頂~晃石山山頂
さっきの巻道へ合流するまで若干滑りやすいルートをたどる。
巻道との合流点に到着。晃石山へ向かう。
南側へ眺望の開けた所へ来た。中央左寄りに見える山が筑波山。
この方角だと真南を向いている。霞んでなければスカイツリーが見えたかも。中央右の水たまりは渡良瀬遊水地。方位角的に、渡良瀬遊水地の上にうっすらと見えるビル群がさいたま新都心。
パラグライダーの離陸場。この写真の左下に写っているレールが荷運び用のモノレール。人が座れるように座席が付いているかも。そうじゃないとパラグライダーをする人が大変だ。林業用のモノレールは山中でよく目にする。
レールはこんな風に下の方へ続いている。よく見るとレールの地面側にアプト式レールのような歯がついているので、歯車を噛ませて上り下りしているのでしょう。これは死ぬ前に一度乗ってみたい!
晃石山山頂と晃石神社への分岐。神社は山頂のすぐ下にある。我々は右手の山頂へ~。
ひと登りで祠が見えてきた。低山だとあっという間に山頂に着くので私は不完全燃焼です。小学生にはちょうどいい運動かな。
晃石山山頂(419m)に到着~。大平山より標高が高くてしかも眺めがよろしいです。ここで昼食を取ることにしました。
うーん、電波が良く入るという意味かな?そんなの画面を見れば分かるだろという気がしないでもない。
晃石山山頂の祠。
祠の向こう、北側には日光連山の眺め。富士山型の山が日光男体山。白根山はおそらく雲の中。禿山になっている足尾山地に並んで左側に皇海山も見えるはずなんだけど、、、雲の中か。
では山頂のベンチで今日の昼食のすき焼きといきますか~。冬の低山だと肉の腐敗を心配することなくパックのまま持ってこれるからよいよい。牛脂でじゅわ~。
具は自宅でカットしたものをジップロックに入れて持ってきた。タレは試行錯誤の結果、モランボンの小さいボトル入りを持ってきた。山頂の周囲にめちゃいい香りが漂っております。〆はきしめんにした。
デザートはリンゴを1個持ってきたのでカラメルソテーに。バターで焼いて、砂糖を振りかけながら両面焼く。仕上げにシナモンパウダー。これも良い香りが辺りに充満しますよ。
中央の奥側にある低山が晃石山から見た、佐野の三毳山(みかもやま、229m)。三毳山の向こう側に佐野インターチェンジがある。美味いランチで満腹になったので片付けて、来た道を戻ります。
温度計が括り付けてあったので読んでみると摂氏6度。自分の手持ちの温度計でも同じ気温でした。ほぼ無風。
周りの景色を楽しんでから下山開始。
晃石山~あじさい坂下駐車場へ下山
真夏にこんな低山を歩きたくはないですが、冬のひだまり山歩きは見晴らしも良くて気に入りました。
パラグライダー離陸場へ戻ってきた。ここで装備を広げるんだろうな~。
見晴良好な休憩用ベンチがあちらこちらにある。
また筑波山を眺める。
このベンチも眺めよし。
ぐみの木峠通過。ここは大中寺への分岐点。眺望は無いものの休憩によし。
これがグミの木?かな?冬だからよく分からん。
全体的にこんな感じの登山道です。
太平山下の分岐点に戻ってきた。帰りは頂上へ登り返さず、この右手の巻道をたどって太平山神社の方へ戻る。
歩きやすい道。
奥宮の辺りまで戻ってきたらこんな張り紙に気付いた。ここまでわざわざ榊を採りに来る人がいるんか?と一瞬思ったけど、ここを通るついでに折って持っていく登山者がいるかも。
榊の所から5分ほどで登山口へ帰ってまいりました。
太平山神社前から筑波山方面の眺め。今日は山日和でした。
朝に登った階段を下る。
シーサー(違
あじさいが咲く頃に来ると駐車場が混むだろうし暑すぎて山歩きどころじゃないかも。
駐車場に戻ってきたら車の数が減っていた。
太平山・晃石山遠望
今回往復した大平山と晃石山を南側から眺めるとこんな感じ。東北道を走っていると栃木I.C.の南側にある通信アンテナの目立つ山がこの二つの山ですね。冬におすすめの低山でした。お疲れ山~。
今回の山行をReliveで振り返る
Relive ‘2020/02/09 大平山と晃石山ピストン’