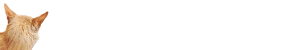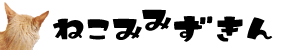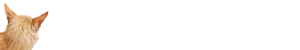| 日程 | 【日帰り】2022年05月05日(木・祝) |
| メンバー | ぬこしち |
| 天候 | 快晴 |
| アクセス | 利用交通機関 車二荒山神社の登山者用駐車場(無料)を利用。 |
最初に日光男体山を登る計画を立てたのはいつのことだったか…。おそらく高校2年の春~夏、1992年のことだったと思われる(30年前だ!)。大学生の頃も計画を立てたことがあるし、その後も登る予定をスケジュールに入れたことがあるのに、毎回毎回天気が悪くておじゃんになったのであった。
2022年のゴールデンウィークは昨年と同様、高速道路料金の休日割引きが無しになってしまい、遠出する気力がなくなった方も多いのではないでしょうか?自分も渋滞に巻き込まれながら長野方面に遠征するのはやだな~、じゃあ先週に引き続きまた日光にしよう!ということで男体山の登山が30年越しでようやく実現することになったのでした。
地図・ルート・標高グラフ・移動ペース
歩行距離:10.4km
累積標高:1,288m(登り)、1,268m(下り)
歩行時間:5時間00分(登り2時間37分、下り2時間22分)
休憩時間:3時間16分
グレード:
コース定数:25.8
コース定数の目安●10前後:体力的にやさしく初心者向き ●20前後:一般的な登山者向き ●30前後:日帰り登山の場合、健脚者向き ●40以上:日帰りでは困難。1泊以上の計画が必要。
行程とコースタイム
- 日帰り
- 行動
- 5時間00分
- 休憩
- 3時間16分
- 合計
- 8時間16分
今回の山行の費用
| 交通費 | 高速 | 浦和~清滝 | 3,450円 | 計 | 6,900円 |
| 清滝~浦和 | 3,450円 | ||||
| 入山料 | 二荒山神社 | 入山料一回分 | 1,000円(大人一回)中学生以下無料 | 1,000円 | |
| 合計 | 7,900円 |
参考リンク
二荒山神社中宮祠・登山者用駐車場から男体山山頂を往復
[05:30]さいたまの方から2時間ほどで着いてしまう日光はやはりお手軽でよい。二荒山神社の登山者用駐車場に車を入れると、その後からぞくぞくと他の登山者もやってきてあっという間に一杯になった。ここの他にも登山者用第2駐車場があるので、困ることはないはず。ただし紅葉のシーズンはどうなるか分かりません。
男体山登山者用駐車場の入口
二荒山神社の建物に挟まれるような感じで駐車場の出入口がある。ここに来るのが初めてで、暗いうちに着くとどこが駐車場なのか分からないかも。
いろは坂から二荒山神社中宮祠へやって来ると、こんな感じの交差点がありますね。右斜め前の鳥居を車でくぐると↑↑の駐車場入口が右側に見えま~す。また、登山者用第2駐車場はこの交差点を直進して「二荒レストセンター」の看板の所で右斜め後ろに入ったところにあります。
登山者用第2駐車場に近い所にあるトイレ。私は気づきませんでしたが、トイレットペーパーが中には無いらしい。必要なら外の販売機で紙を買わねばなりません。
二荒山中宮祠境内で入山料を支払う
[06:07]二荒山中宮祠は朝06:00ちょうどになると太鼓を叩いて開門を知らせてくれます。トイレへ行って駐車場へ戻ってもたもたしていたらそのタイミングを見逃してしまった。音だけ聞こえた。
「願いかなえマス」。金ピカのマスを祀ってあるよく分からない神社?が脇にあった(笑)。バブルの頃のフジテレビのようなセンスだこりゃ。他にも金ピカの龍がとぐろを巻いている像もありました(笑)。
登山者必読!の注意書き。
境内に入ると氏名、住所、下山予定時刻などを記入する受付用紙が置かれた台があるので、そこで記入する。
そして受付で入山料1,000円を支払うと、チケット代わりに首にかけられる白いお守りを渡されます。以前は500円だったのに、いつの間にか2倍になっとるな~。
石れざさ。筑波山にもあったな。

境内の奥にある登山口の鳥居。赤い門をくぐると男体山登山道の始まりです。登拝道の方が正しい呼び名かも。
男体山山頂までの登り
一合目から三合目まではブナやミズナラなど広葉樹林の中を登る。三合目から四合目は砂防工事用の舗装道路を歩くので急に歩くペースが上がります。
四合目には土台がコンクリの比較的新しい社務所があった。
二荒山神社中宮祠に掲示されていた注意書きにもあった、四合目の白い鳥居がこれ。ここから再び登山道に入ります。この鳥居前は開けたスペースがあるので荷物を下ろして休憩する人も多い。
[07:25]五合目に到着。登り始めから1時間ちょいで男体山の半分。
五合目にも小屋があった。
中を覗いてみると、金目のものは無かった(笑)。
[08:15]七合目は視界が開けて中禅寺湖と半月山方面がよく見え、ホッと疲れが取れる。
こちらが七合目の避難小屋。高度を上げるにつれ小屋がボロくなってきます(笑)。
七合目の上はガレ場の登りになります。不安定な大きめの岩もあるので落石注意。足元ばかり見ずに上の方もちょいちょい確認しながら。
突然現れた鉄製の赤い鳥居は八合目の神社のものらしい。
ここには瀧尾神社があるとのことだが、これかな?横に古いタイプの鎖がある。昔と今ではルートがずれているのだろうか。
瀧尾神社の社務所もしくは避難小屋。受付の台のようなものと大きめの窓があるから社務所かな~?地図では八合目避難小屋と記されている。瀧尾神社の本社は東照宮の裏手の方にあり、氷爆で有名な「雲竜渓谷」へ向かう道の途中の森の中にひっそりとたたずんでいます。
瀧尾神社本社の位置はここ。
男体山八合目まで登ると社山や右奥の皇海山が見えるようになった。空が霞んでいなければ富士山も見えるはず。
そして樹木の背も低めになってきたので、あとちょい登れば森林限界を超えた山頂付近になるもよう。
4日前の5月1日に低気圧が通過し、雪を降らせたのでその名残がまだありました。
念のためにチェーンスパイクを持参しましたが、使うに及ばず。朝だからまだいいけど、下山時は雪が溶けてぐちゃぐちゃになってそうだな。
[09:44]九合目を過ぎると北西の視界が開け、戦場ヶ原の向こうの日光白根山の白い姿が見えるようになりました。
白根山の南側、中禅寺の西岸(千手ヶ浜)の奥にある西ノ湖は昔は中禅寺湖と繋がっていたようだ。繋がっていたというか、堆積物による陸地化が千手ヶ浜まで進んできていると言った方がいいか。中禅寺湖もそのうちいつかは尾瀬ヶ原のような湿原になるのでしょう。
[09:46]森林限界の上に出ると赤茶けた溶岩がザレザレした登りになります。
日光白根山の北方、福島県側の雪をかぶった山々もみえるようになった~😻
まだ山頂に着いていないのについつい立ち止まってこの箱庭のような景色に見とれてしまう。
日光男体山山頂にて
[10:04]休憩込みの4時間で男体山山頂、二荒山神社奥宮に到着~。ここにはWEBカメラ(赤丸の所)があり、毎時59分59秒に撮影しています。パナソニックのカメラだ。通常は朝04:14:59から18:59:59まで明るいうちに稼働していて、「男体山登拝大祭」期間中になると24時間、毎時59分59秒に撮影しているそうだ。
こちらは男体山の北側の眺め。さいたま市から見ると太郎山は男体山の後ろに隠れてしまって見えにゃいな。男体山の右側に聳える女峰山は、冬の空気が澄んだ晴れの日ならさいたまからでも見えます。
手前の太郎山と、奥の方にまだ白い姿をさらけ出しているのは福島の会津駒ヶ岳とその周辺です。
日光白根山と会津駒ヶ岳の間には尾瀬の至仏山や燧ヶ岳がよく見えます。
さらに左側、中禅寺湖とその向こう側の山並み。赤城山まで見えた。社山の奥の山肌が茶色くなっている場所は足尾銅山の煙害の名残です。中倉山に有名な孤高のブナがありますね。
男体山山頂から尾根伝いに太郎山神社まで行くとインスタ映えする写真が取れる絶景ポイントがあります。あの先っぽの岩の上。わしは高所恐怖症なので遠慮しときます。ブルブル。この太郎山神社の岩をこちらから見て左側から巻くと2,397m地点の三等三角点へ進むことができ、そのまま三本松の戦場ケ原開拓之碑へつながるルートがあります。ありますというか、かつて存在した登山道ですね。
男体山の三本松ルート
私が高校1年の時(1991年)に購入したエアリアマップ(山と高原地図)には、その古の三本松ルートが破線で描かれています。調べてみると今でも三本松ルートを使う人はいるようで、ヤマレコやYAMAPに記録が上げられている。二荒山神社としては入山料を徴収できない(しにくい)三本松ルートは潰したかったんでしょうな~。志津ルートは日光修験道の一部であり、1200年も歴史がある古道なので潰せないでしょう。しかし登拝門前に書かれていた、ここが「男体山頂奥宮への唯一の登拝口」という文言は気に入りませんな。唯一ではない。
もうちょい山頂を散策
この写真が一番いいな~。もうちょい空が澄んでいればよかった。ちなみに中禅寺湖水面の標高は1,269mで、男体山山頂(2,486m)との標高差は1,217mもあります。この標高差がありすぎるため、男体山は初心者向けではないと言えます。
二荒山大神。

太郎山神社とは反対方向に男体山の最高地点(2,486m)があります。ステンレス製の大剣が突き出ていて、写真撮影の順番待ち中。
シャキーン!!青空にステンレスの刃がよく映える。
意外と足場が狭いのでちょっとビビる。
近くにあった一等三角点(2,484m)。
名残惜しいけどそろそろ下山しますかね。
男体山のもう一つの登山口である志津乗越へはこの先、北面へ下る。志津乗越から奥に見える大真名子山、小真名子山、女峰山へと縦走できます。できるけど避難小屋泊になるうえに、水の補給がキツいでしょう。
男体山山頂は広いのでランチ休憩する場所には困らない。
大剣の刃の薄さ。ここに落雷することはあるんだろうか?
華厳の滝周辺の建物群や滝の下流の大谷川に削られて出来た谷の地形がよく分かる。昔は華厳の滝の駐車場から茶ノ木平にロープウェイが繋がっていて、今でもその索道跡が一本の筋になって残っている。
大谷川の作り出したダイヤキャニオン。この写真の左、大谷川の下流に東照宮や日光駅前の市街地があります。
なんだかここはあちこちに「男体山山頂」の標識があるな(笑)。
山頂には二荒山神社所有のものと思しき廃墟があり、その裏にこんな木造の構造物があった。なんだろこれ?形的に古いタイプの便所かな?屋根と壁と扉が無くなっているが、便槽のようなものがあるし。昔の垂れ流しタイプの便所の廃墟だということにしておきます(笑)。
これが男体山山頂の廃墟。神社の所有物で、社務所兼登拝者用の休憩所だったはず?今にも崩れそうになっているので立入禁止のロープが張られています。
「宇都宮、日の丸講」と記されている鐘。
登ってきたルートをそのまま引き返して下山
[11:31]下山開始。
男体山上部の赤茶けた溶岩ザレザレ地帯を中禅寺湖を眺めながらサクサク下る。
やはり昼には雪と土が混じり合ってドロドロぐちゃぐちゃになってました。
[12:50]ここは六合目で、いろいろ崩れている場所。
[13:01]五合目の避難小屋前からの眺め。だいぶ高度が下がってまいりました。
[14:19]ようやく一合目に下りてきた。
一合目の遥拝所。
足清め所という名の登山靴洗い場があるので、靴底などについた土を落としておきます。昔の人は男体山の土を持ち出さないようここにわらじを脱ぎ捨てたので、草鞋の山が出来ていたそうです。
登拝門の狛犬。神社によって形が違うのが面白いですな。
男体山の登山道(登拝道)への出入口である登拝門全景。「唯一の登拝口」と書かれていますが、反対側にある男体山北面の志津乗越からも登拝は出来ます。かつて存在した、三本松と太郎山神社を結ぶ登山道(三本松ルート)は、一般ルートではなくなってから久しいようです。
登拝門とその前の鳥居全景。右下に悪趣味な金ピカの龍がいる。
色々な注意書き。上にトイレや水場はありませんので注意。携帯トイレと目隠し用のツェルトを持っていくといいでしょう。森林限界より上の山頂近くになると、隠れる場所はなかなか無いと思います。
携帯トイレ用のブースを避難小屋の隣りに設置したり、使用済みの携帯トイレを捨てられるゴミ箱を登拝口の近くにでも設置してくれるといいけど、神社の境内や御神体そのものの男体山だと難しいですかね?
男体山の山バッジも500円で購入。デザインは4種類もある。さすが人気のある百名山だ。
二荒山神社中宮祠の正門前から仰ぎ見る男体山の山頂。30年越しの計画が実現してよかったよかった。
二荒山神社周辺の桜と中禅寺湖。
5月5日でちょうど満開を過ぎたくらいでした。今回は温泉に入る時間がなかったのでこのまま車で帰還。